|
(a)
|
(b)
|
|||||||
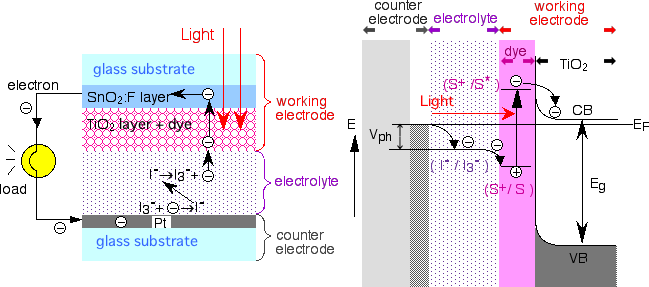
色素増感太陽電池の(a)模式図, (b)原理図. |
||||||||
|
色素分子はTiO2半導体作用電極表面に吸着した状態にあります。ここに太陽光が入射すると、色素分子は光を吸収して励起状態となり、TiO2の伝導帯へ光電子を注入します。光電子はTiO2層、下層の透明導電層を通過して外部回路へ取り出された後、対電極を通じて電池内へ戻ります。この対電極と作用極間には電解液(I-/I3-)が存在します。I3-は対電極でI-へ還元された後、作用電極まで拡散し、ここで先に電子を放出してカチオンとなった色素分子を還元すると同時に、I-自身は酸化されI3-として再生されます。このようにして、光を電流へ変換する酸化還元のサイクルが完成します。また色素分子を利用することで太陽光の吸収を可視領域にまで拡げることに成功したこのシステムは、原理的に自然界の光合成に類似しているため、別名『光合成模倣太陽電池』、或いは発明者の名を冠した『グレッツェル電池』と呼ばれています。
|
||||||||
 |
 |
|||||||
|
色素増感太陽電池の実演
|
||||||||
| 太陽電池の特性は、太陽電池評価装置を利用して疑似太陽光下(AM-1.5)で行っています。測定装置内部は疑似太陽光の反射や散乱を防ぐとともに、外部の光を遮断するために黒く塗られています。 |
||||||||
 |
 |
|||||||
|
色素増感太陽電池評価装置(分光計器). (a)全体, (b)測定室.
|
||||||||