| SPD装置の模式図を図1に示す。二流体式SPD法は、まず一定の距離だけ離したホットプレート上のガラス基板に、圧縮空気をキャリアガスとしてアトマイザーから原料溶液を噴霧することから始まる。この装置では、たとえ少量の噴霧であっても5〜10℃の基板温度の低下があるため、これを一定に保つためには噴霧を一旦中止し、当初の温度に回復するのを待ってから再び吹きつけるという、間欠的な操作が必要になる。従来のSPD法では全てこの点を無視する傾向にあり、我々は液滴の噴霧を間欠的に行うことで良質の薄膜が得られると考えている。基板に到達した微小液滴は溶媒の気化・蒸発に伴い濃縮および乾燥し、図2のような経路をたどって原料化合物から薄膜が形成される。すなわち、溶媒に存在する物質の熱分解や化学反応によって目的物質の固相が析出し、基板に堆積する。雰囲気中のガスよりも、むしろ微小液滴の均質性や粒径分布が熱分解過程に強く影響するので、良質の薄膜を形成するためにはこれらの点を充分考慮する必要がある。 | |
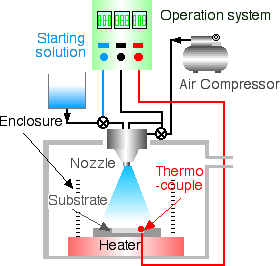 |
 |
|
図1.二流体式SPD製膜装置の概略
|
図2.SPD法による薄膜形成機構
|
SPD法における液滴の変化過程は、ViguiéとSpitzが提案したモデルに基づき、基板温度の上昇によって図3のように分類することができる。図中のAが本来のスプレー熱分解である。液滴は溶媒の蒸発に伴って小さくなるが、なお溶質を含んだ状態で加熱基板に到達する。以後、溶媒が完全に蒸発して残った溶質は熱分解・化学反応する。Bでは溶媒は完全に蒸発して溶質が固相または液相となって基板に到達する。CはCVDと類似していて、溶質は溶媒が蒸発後、固相または液相から昇華や蒸発により気相として基板に到達する。Dは基板温度が最も高く、溶媒の蒸発と溶質の気化が素早く起きて熱分解し、生成物は薄膜ではなく、粉末状で基板に堆積する。AとDはどちらも単独で進行する条件を容易に設定できるが、BとCは必ずしも単独に進行するのではなく、他の過程と同時に起る可能性が高い。 |
|
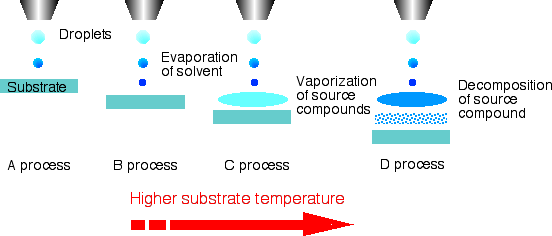 |
|
|
図3.基板温度に対してモデル化したスプレー熱分解過程
J.C. Viguié and J. Spitz, J. Electrochem. Soc., 122 (1975) 583. |
|